アレルギーとは?
人間の体にはもともと免疫というシステムが備わっており、さまざまな病気を乗り越えて生き延びていくのに必要不可欠なものです。免疫とは「疫病を免れること」であり、「自己(自分自身の細胞)」と「非自己(抗原=体外から入ってきた異物)」を区別して、後者を攻撃・排除する機能です。このように免疫反応は人間にとって重要な防御機構であり、通常は生体にとって有利に作用しますが、時としてこの機構が過剰に働くことでさまざまな障害を呈することがあります。これがアレルギーです。
アレルギー(allergy)の語源はギリシャ語のallos(other:変じた)とergo(action:作用・能力)に由来し、「変じた反応能力」という意味で付けられたとされています。
またアトピー(atopy)は、「奇妙なこと」「異常」を意味するギリシャ語「atopos」に由来しています。今日の定義からするとアレルギーとは、「免疫反応に基づく生体に対する全身性ないしは局所性の障害」です。分かりやすく言い換えると、免疫システムの側からは良いことをしているつもりが、体にとっては不利益な症状になってしまうということです。
代表的な例として、身近な花粉症をあげてみましょう。花粉症の患者さんは、抗原となる花粉が鼻や目に入ると鼻水や涙が出ます。人間の体には鼻や目に異物が入るとそれを洗い出そうとするシステムが備わっていますが、花粉症の患者さんはその機構が過剰に作用し、かえって不快な症状となってしまうわけです。
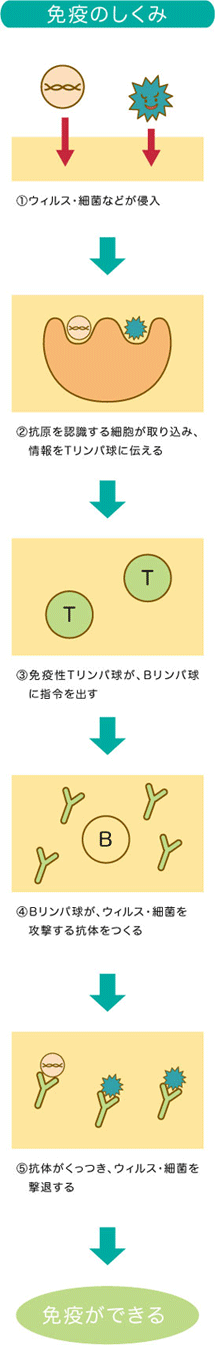
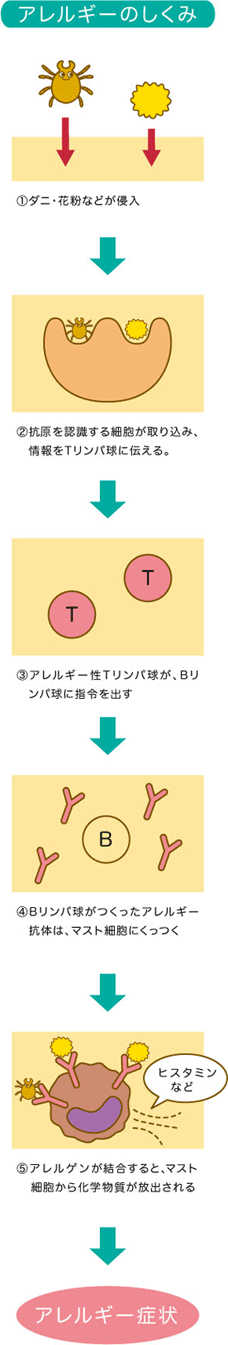
なぜアレルギーが増えているか?
アレルギーをもつ人は近年増え続けていて、いまや国民の三人に一人は何らかのアレルギーをもっているといわれています。アレルギー人口の増加の背景には、環境の変化や食生活などが関係しているといわれています。たとえば近年の住宅は高気密・高断熱であり、ぜんそくやアレルギー性鼻炎の原因となるダニが繁殖しやすい環境であるといえます。また自動車の排気ガスなどによる大気汚染も、ぜんそくの悪化原因とされています。
また戦後大量に植林されたスギの木の影響で、花粉症の患者さんが非常に増えています。また食生活の欧米化で動物性タンパク質や脂肪の摂取が過剰となり、食物アレルギーの発症に関係していると考えられています。
どのようなものがアレルゲンとなるか?
アレルギー反応を引き起こす抗原のことを、アレルゲンといいます。
大きく分けて、①食べるもの
(食餌性アレルゲン)、②吸い込むもの(吸入性アレルゲン)、③触れるもの(経皮性アレルゲン)に分類されます。
食餌性アレルゲンとしては、卵・牛乳・小麦・大豆・ソバ・ピーナッツ・魚類・甲殻類などがよく知られています。
吸入性アレルゲンにはダニ・カビ・ペットのフケ・花粉などが含まれ、ぜんそくや花粉症の原因となります。
経皮性アレルゲンは、じんましんなどの即時型反応をおこすものと接触性皮膚炎という遅延型反応をおこすものに分けられます。ハチ刺されやゴム手袋着用(ラテックスアレルギー)などのケースが前者に属し、接触後30分以内に症状が出現してアナフィラキシーという重篤な症状に移行することもあります。一方ネックレスなどの金属類や化粧品などによる皮膚症状は接触性皮膚炎とよばれ、接触している限り慢性的な症状を示します。
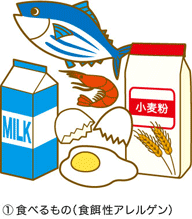
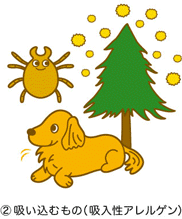
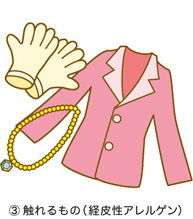
アレルギーの検査法は?
アレルギーの病気を診断していくうえで、原因となっているアレルゲンを特定する必要があります。
まず血液検査では、血液中のアレルゲン特異的な IgE 抗体の量を測定します。しかし気を付けなければいけないのは、原因と思われるアレルゲンに対する症状があっても IgE 抗体の数値が低い場合や、逆に IgE が高値でも症状とは関係がない場合もあります。つまり血液検査での IgE 値はあくまで参考であり、結果をそのまま鵜呑みにすべきではないということです。
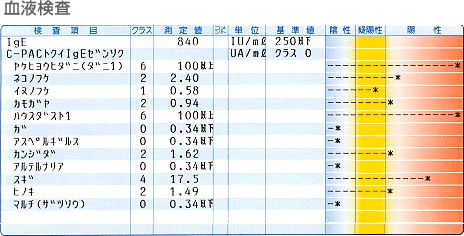
血液検査で診断がつきにくい場合、皮膚テスト(プリックテスト)が有用なことがあります。アレルゲンエキスを皮膚に 1 滴たらし、検査用の針を皮膚の表面に押し当てて、15分後の反応をみます。アレルギー反応がおきるとアレルゲンエキスをつけた皮膚の部分が赤く腫れ、その程度により陽性かどうか判定します。生体そのものの反応をみているので、血液検査よりも鋭敏だと考えられています。
